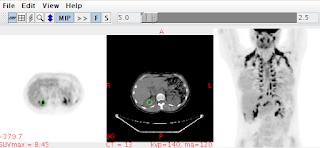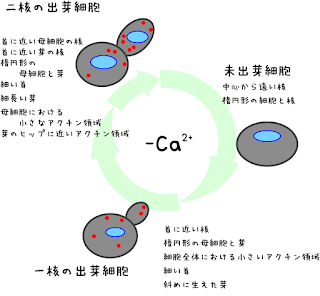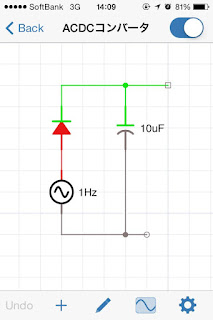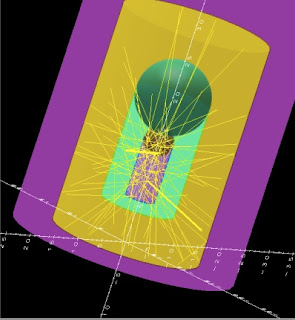【残り82日】初めての140点代に。あとは問題集をやりこむか。

というところまで来ました。 そして、そうか、もう2ヶ月あまりしかないのかという気持ちになっています。 10月〜やってきたことは、以下の通り ①学校の授業を集中して聞く ②学校の教科書を一から読み直す ③語呂合わせを作る ④過去問を解く でした。主に②が一番メインでした。学校の授業で聞いてきたことを自分の言葉にする為には、教科書を一から「読み物として」読んでみるというのが良いだろうと思って、放射線概論や、X線解剖学や、機器工学や、MRIや、CT、核医学などの教科書を読みました。教科書が無い場合は、学校の図書館で放課後1時間くらい読んでみました。 そうすると、自分が授業で聞いて分かった気になっていたことが実は勘違いしていたり、理解が不足していたんだな、、ということが分かったのでした。 試験前に慌ててその単元のノートをひっくり返し、授業でやってた内容をおさらいする、という勉強を定期試験ではやっていたし、一種も分かんないところは解答を覚えてしまえ、という感じでやっていたのですが、国家試験の勉強の仕方は違うと自分は思います。 その先、就職してから、得た知識を活用していく必要がある訳だから、自分が勉強した内容をある程度理解し、咀嚼し、現場で同僚達と前提知識を持ってコミュニケーションをとらなければいけません。 そんな時、学校の授業のように、分からないことに対して一から教えてくれることはありません。自分で情報をとりにいき、本当にそれが正しいのかどうか、それにどんな意味があるのかを確認出来る力が必要です。 そこで、前述の勉強方法をとっていました。本を読み、その内容を咀嚼すると分かることが色々あります。そして、勉強が功を奏して、劇的に点数が上がりました。 実習明けの10月の模試では、100点でした。先週の模試は28点、それから今日の試験では42点あがりました。その間、参考書は問題集だけを買いました。あとは必要な本は図書館で借りています。 参考書は、自分が勉強した知識に抜けや漏れが無いかを確認する手段としては良いと思います。ただ、前提となる知識が不十分だなと思う時は、一から技術書を読み直すことが必要だと思います。 参考書の中でも、情報をまとめただけになっている本は、何らかの原本をまた参考にしており、まとめる際に筆者が間...