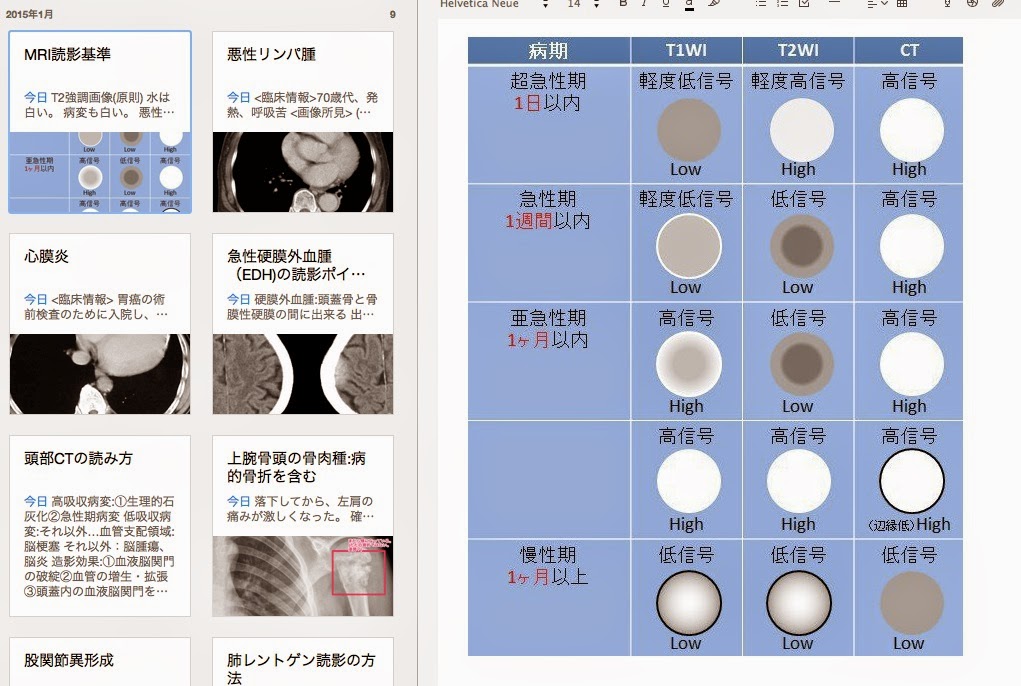サイトのリンクを更新しました。
ここ5~6年ほどでリニューアルなどで無くなったサイトもあったため、 古くなっていたリンク集を更新しました。 過去問集 https://houshasengishi.blogspot.com/p/blog-page_12.html 参考リンク https://houshasengishi.blogspot.com/p/blog-page.html 今後も更新していきますので、よろしくお願いします。
このブログは、勉強しつつ少しずつ学んだことを記事にします。不定期的に記事を見直して更新しています。