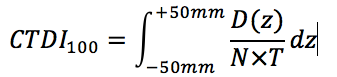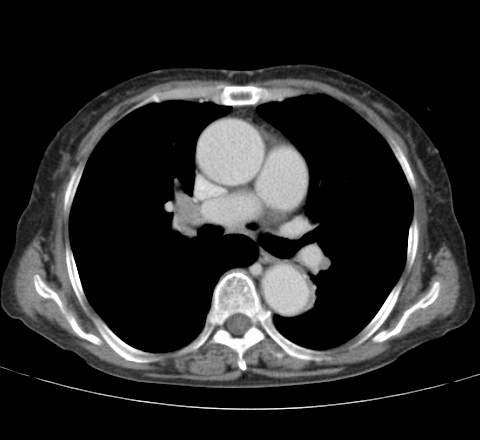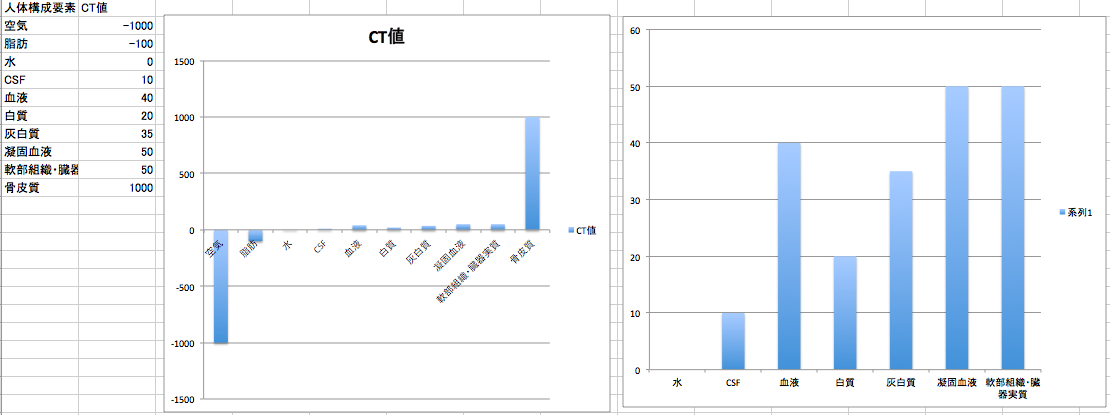斜め読み:コロナウイルス(COVID-19)に対するCT検査の考え方について
AuntMinnieというアメリカの診療放射線関係のメディアによれば、ACR(米国放射線学会)がコロナウイルス(COVID-19)に関するステートメントを3月初旬に出していた。 ACR recommends sparing use of CT for COVID-19(March 11) https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&ItemID=128426 要約すると、以下の通り ・スクリーニングにCTはあまり有効じゃない。(Clinicians should not use CT as a first-line or screening test to diagnose COVID-19.) ・診断がついて入院してる患者さんの経過観察で使った方が良い。(Clinicians should reserve CT use for hospitalized, symptomatic patients with specific clinical indications for CT.) ・患者をスキャンする際は感染源を増やさないように適切な処置をすべきだ。(Facilities should apply appropriate infection control procedures when scanning patients.) ・必要に応じてポータブル撮影も必要かも(Facilities may consider using portable radiography units when x-ray is medically necessary.) ・撮影したら撮影機器は滅菌し、1時間は撮影室の使用禁止すべき(換気率による) (facilities consider not only thoroughly cleaning medical imaging machines and devices but also suspending use of imaging rooms for roughly one hour between imaging infected patients, depending on the roo...