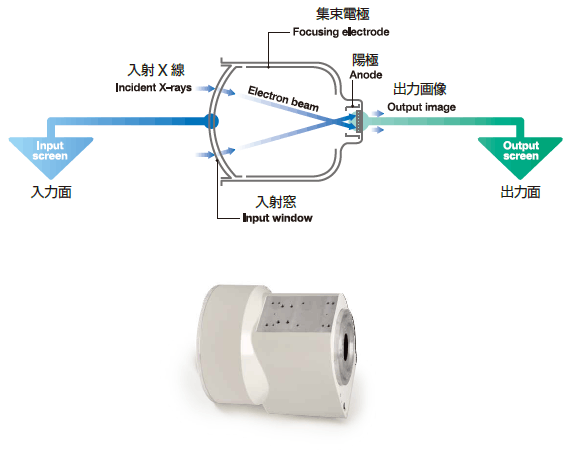呼吸同期と間欠照射について@学園祭
先日、母校の学園祭に行き、上記の演題の学生発表を聞いてきました。以下、今の自分の知識の中で、演題についてまとめてみます。細かいところ、おかしいかも知れないので、あとで調べますが、「どんな話だったのか?」というエッセンスが伝わればと思います。 放射線治療では、治療計画を行う時に、CTを撮影して、その撮影画像のCT値から逆算して、線量をシミュレーションします。(電子密度変換テーブルというのを習ったと思います。) ただし、治療計画CTの画像は、身体の体動まではシミュレーション出来ません。実際に照射する時の誤差としてinternal marginとかset up marginなどが出てくるのでしょう。(GTV、CTV、PTVとかそのあたり?) 肺の放射線治療の場合、初期であれば効果があるけれど、限局したところにかなり線量をかけて行う方法をとっているので、体幹部の誤差よりも厳密にしないといけません。 その為、腹部と胸部の両方の呼吸をモニタリングする仕組み(abches)を使って、リアルタイムの身体の位置を調べながら(RPM:realtime plan monitoring)照射を行うことで、体動による照射線量の誤差を減らします。 同じ呼吸相のタイミングで(例えば吸った時だけ)照射するので、ずっと照射する訳ではなく、1回ずつ間隔をあけて照射します(間欠照射)。 ただ、X線出力は、診断装置でもやったように、コンマ秒単位で見れば、立ち上がりと立ち下がりがあるので、毎回ぱつぱつやっていたら、立ち上がり、立ち下がりの部分が実は照射線量の誤差になってるんじゃないか?と考えてもおかしくはないだろうと。 そこで、事前にMUの基礎検証=出力精度、再現性、均一性を調べて、実際、同じ間欠照射のプランで試しにファントムで検証したらどうなるんだろう、という話を学園祭ではされていました。(解釈が間違ってなければ) ただ、ちょっと専門用語とか治療の知識が全然追いつかず、300MU/minという値が実際、高いのか低いのか、MU値ってそもそも1MU=何Gyだったっけ?というのを忘れてしまいました。。今、本で調べたら、DMU(Dose Monitor Unit)はcGy/MUでした。下限値7MUということは7cGy=0.07Gyということですね。 厳密に1MU=1cGyが達成...





.JPG)