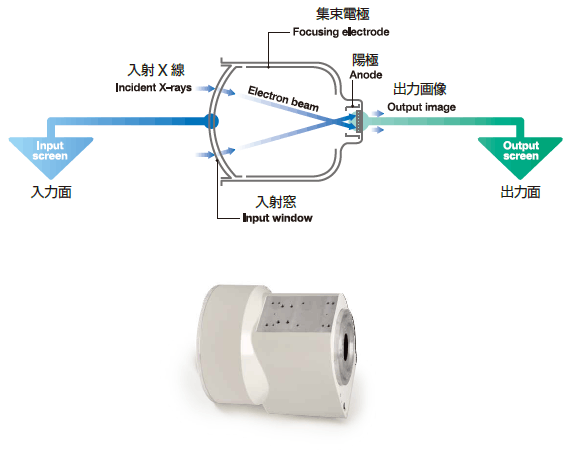腰椎:前屈位撮影・後屈位撮影
腰椎には生理的湾曲があり、焦点間距離が一定でない。従って、これを調整する為に前屈みになるか後ろに身体をそらすかして、湾曲を補正しないといけない。 ポジショニングする時、患者さんの腰回りを持って調整すると思う。 前屈位撮影 体位:立位・座位または側臥位で両下肢を下垂。可能な範囲で胸腰部を前方へ屈曲 側方から見た時、胸部側と骨盤部側がねじれていない(回旋していないことを確認) 両サイドどちらかに回旋していると、きちんとした腰椎像が確認されない。 後屈位撮影 体位:立位・座位または側臥位で両腕をくみ、上半身を背面に可能な範囲で傾ける。視線も上方を向く。 立位の場合は、膝を進展、側方から見た時、胸部側と骨盤部側がねじれていないことを確認する。=真側面かどうかを確認する。 (身体がねじれていないかどうかはCTやMRIの時も確認する。軸がずれていると、CTやMRIの撮像中心がずれてしまうから。見慣れている画像は全て体軸が正中線上にある状態で撮影している) 確認点:L1〜L5にかけての椎体前面に沿ったラインとL1~L5にかけての椎体後面に沿ったラインが滑らか。