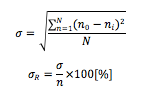放射線スペクトルデータをWeb上で閲覧出来るSPViewerについて
先日、Safecastの4周年のイベントがあり、NHKのスーパープレゼンテーションにも出演される伊藤穣一さんなどの講演を間近で聞くことが出来る会に参加しました。色んな形のGM計数管装置などもあり、様々な海外の計測器、仕組みについて見ることが出来ましたので、そのうちブログで紹介すると思います。 その際に少し、出てきたものの紹介。 http://www.mikage.to/radiation/spviewer/ http://safecast.media.mit.edu/radangel/spviewer/ SPviewerは放射線測定器のスペクトルデータをWeb上で表示できるツールです. 放射線測定器では、身の回りの放射線の強さを調べています。時系列でエネルギーの偏りを調べて、どのエネルギーが一番多いかを調べることが出来ます。測定器には計測するセンサーがあり、そのセンサーで検知した放射線の数をもとに放射線の強さを調べています。 しかし、測定器がそれ自体で完結していて、データをパソコンに取り込む方法が分からないことがありませんか? 個人や民間の方が放射線測定器で調べたスペクトルをよく画像等でネット上に公開していますが、SPviewerを使えば、PCのソフトウェア上で生のデータを取り扱うことが出来、拡大、縮小、比較、再解析を行うことが出来ます。 皆さんが自前の測定器で計測されたスペクトルデータがあれば、SPViewerに取り込んで頂ければ、無料で解析頂けますし、Webページにアップして使うことも出来ます(MITライセンスで配布)。また、Dropbox を使えば,Webページを持っていない方も簡単にスペクトルを公開できます。 以下がより専門的な使い方は、SPviewerで出来ることです。 対応機種のスペクトルデータの表示 片方をバックグラウンドとして,2つのスペクトルデータの比較・差分表示 最大5つまでのスペクトルを比較表示 スペクトルグラフの拡大表示・対数表示 スペクトルの付随データ(計測時間や検出核種)の表示 カーソル位置のチャンネル番号・エネルギー・cpsの表示 カーソル位置近傍のエネルギーを放出する核種の表示(上位5件) 1スペクトル表示時:選択範囲のグロスc...